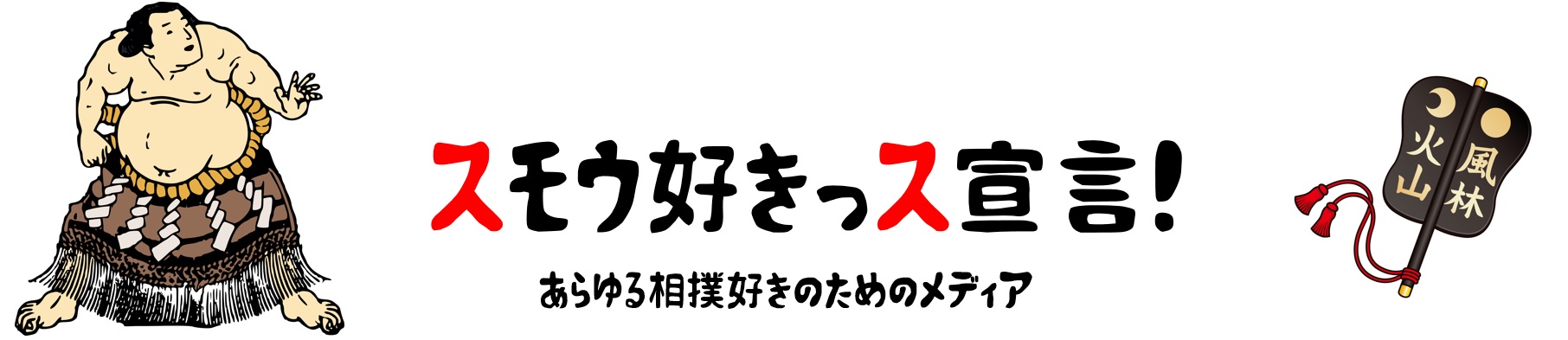前頭(まえがしら)
三役(大関、関脇、小結)の次の地位。いわゆる「平幕」とよばれる幕内力士。
横綱、三役以外はすべて前頭〇枚目、と番付がつく。
前さばき(まえさばき)
立ち合いで、両社が互いに差し手を争うこと。得意の差し手を入れるのが上手い者、前哨戦が上手い者を「前さばきが上手い」という。
前相撲(まえずもう)
入門した直後の力士が本場所で取る相撲。現在では、前相撲での成績にかかわらず参加した全力士が「新序出世」し、出世披露の後に序の口の番付に載る。
前ミツ(まえみつ)
まわしを腰に巻いたときに前に来る部分。陰部を覆っている部分ではないので要注意。
髷(まげ)
力士の長い髪を束ねて結んだもの。大銀杏とちょんまげの2種類がある。
桝席(ますせき)
四角い桝の形に区切っている席のこと。飲食が可能で桟敷の次に席料が高額な席。土俵との距離が近い席や花道に近いところが高額になりがちだが、席料としては一人当たり1万円以上が目安となっている。
待った(まった)
立ち合いの際、一方の突っかけに対してもう一方が立たないこと。原則として制限時間以降の「待った」は許されない。なかなか立ち合いが合わないと結びの一番の取り組みがTV中継の枠に間に合わなくなるため、審判部の親方から叱られることもある。(特に幕下以下)
回し団扇(まわしうちわ)
行司が間違いかけた自分の判定を訂正するために、軍配を反対側にぐるりと回して上げること。
まわしを切る(まわしをきる)
相手にいったん取られたまわしを離させること。手でひねったり、腰を振ったり、肘を張るなどの手法でまわしを切ることができる。
満員御礼(まんいんおんれい)
本場所で観客席のほとんどが埋まること。吊り屋根の上から「満員御礼」と書かれた垂れ幕が下がる。垂れ幕が下りると、相撲協会から関係者に通常10円玉入りの大入り袋が配られる。
水入り(みずいり)
十両以上の取り組みでなかなか勝負がつかず、両者の動きが止まった時に審判委員の承諾、もしくは指示を受けて行司が勝負を中断させること。(目安は4分)
力水を付けるなど休憩後に、中断前の姿勢に戻って取り組みを再開する。
耳が湧く(みみがわく)
稽古によって耳がこすれて、肉が盛り上がって変形すること。柔道やラグビー選手にもみられる現象。
向う給金(むこうきゅうきん)
負け越しが決定すること。十両以上は8敗、幕下は4敗することを指す。
虫眼鏡(むしめがね)
序の口力士のこと。番付に載った四股名があまりにも小さすぎるため、探し出すのに虫眼鏡が必要なところから生まれた俗語。
結びの一番(むすびのいちばん)
その日の最後の取り組みのこと。
胸を出す(むねをだす)
ぶつかり稽古の受け手となること。
目が開く(めがあく)
本場所で連敗していた力士が、1勝目を挙げること。「初日を出す」ともいう。
目を出す(めをだす)
勝負に勝つこと。本場所ではなく稽古場でよく使われることが多い。
申し合い(もうしあい)
同等の実力を持つ力士数人が、勝ち抜き形式で稽古をすること。
物言い(ものいい)
行司の判定に納得がいかないときに、土俵下にいる審判委員が異議を申し立てること。
差し違えか、同体取り直しかを判定し、正面審判庁が結果を場内にアナウンスする。
なお、土俵下の力士も物言いを付けることができるが、審議には参加できない。